京急新1000形は2002年(平成14年)に登場した電車です。
マイナー(?)チェンジを繰り返し、14年以上経った現在でも製造が続けられており、
保有車両数も京急最多となり、京急の主力車両です。
正式名称は1000形ですが、登場時にまだ初代の1000形が残っていたため新1000形と
通称で呼ばれています。
なお、2011年3月末に初代1000形が完全に引退しましたが、2016年12月現在も公式発表
などでは引き続き新1000形が使用されています。また、アルミ車とステンレス車も明確に
分けられています。なお、1800番台もステンレス車両ですが、従来のステンレス車と
分けるために、ステンレス車ではなく、1800番台と呼称されています。
2017年2月現在、8両編成が24編成、6両編成が14編成、4両編成が26編成の計380両が
在籍しています。アルミ車は8両編成が9編成、4両編成が12編成の計120両、ステン
レス車は8両編成が15編成、6両編成が14編成、4両編成が14編成の計260両です。
電動車は278両、付随車は102両です。
廃車は発生していません。
1601編成の登場により、歴代1位の製造数を誇った初代1000形の記録を抜き、1位と
なりました。
外観
--------------------------------------------------------------------------
車体材質はアルミ製とステンレス製の2種類があります。
当サイトではこれ以降、アルミ製の車両をアルミ車、ステンレス製の車両のうち、
1800番台以外の車両をステンレス車、1800番台が付与された編成は1800番台と
表記します。(特記ある場合を除く)
アルミ車、ステンレス車は、前面向かって左側に非常用ドアが設置されています。
1800番台は前面中央に貫通扉を設置し、幌を繋げられるようになりました。
アルミ車、ステンレス車は前照灯や急行灯、尾灯には電球が採用されていますが、
1800番台はともにLEDが採用されています。
3タイプすべての先頭車にはスカートが設置されています。また、車体側面は両開きの
3扉となっています。また、窓にはカーテンが設置されています。
車側灯は7次車までは電球式でしたが、8次車からはLED式が採用されています。
既存車両も順次LED化されました。
アルミ車の車体は、赤い電車で窓周りにはアイボリーの塗装が施されています。前面は
600形や2100形の前面をほぼ引き継いだ形状になっており、2100形には特に類似して
いますいます。同様に、ワイパーはワイパーカバーに収納されています。また、この
カバーには切り抜き文字で「1000」と表記されています。
窓は開かないため、排気扇を設置しています。
ステンレス車はJRのE231系を参考に設計されました。雨樋等が露出する形で設置
されたため、地下鉄乗り入れ規格に合わせるため上に向かって絞り込まれています。
なお、車体の構造には変わりありませんが、外装や内装の違いにより、前期型と
後期型のステンレス車がいます。1800番台についてはその項目を参照してください。
前期ステンレス車は、窓下に幅広の赤と白の帯のフィルムが貼り付けられています。
また、窓上には赤のフィルムが貼り付けられています。太いフィルムを使用しているため、
他社の一般的なステンレス車と比べステンレス部分が目立ちにくくなっているのが特徴
です。なお、車体工法の違いにより、川崎重工製の車両の窓上の帯が東急車輛製の
車両と比べて若干細くなっています。ワイパーカバーは廃止されました。窓が開くように
なったため、排気扇は設置されていません。
1800番台の車体はステンレス車と同一のものですが、側面がフルラッピング仕様に
なり、カラーリングはアルミ車に近いものとなりました。前面形状は前述したとおり、
中央に貫通扉が設置されたものの、デザイン的にはこれまでの新1000形に似せて
あります。
1800番台製造以降に製造された後期ステンレス車は従来の顔に戻りましたが、
側面は1800番台と同様にフルラッピング仕様となりました。また、車外スピーカーも
京急社で初めて採用しました。
従来、京急の無線はIRでしたが、2014年10月に1489編成にSRアンテナが取り付け
られました。以降、順次SRアンテナを取り付けています。
内装
--------------------------------------------------------------------------
アルミ車の車内は扉間と乗務員室後部がロングシート、車端部がクロスシートとなって
います。
前期ステンレス車、1800番台の車内は全てロングシートとなっており、乗務員室直後は
座席は設置されていません。後期ステンレス車は、乗務員室直後を除き片側ずつ
クロスシート(ボックスタイプ)が復活し、乗客が自由に使用することができるサービス
コンセントが2口設置されました。
9次車までの車両のドア上部には京急LED式の車内案内表示器が設置されています。
ドアチャイムも設置されています。10次車からはLCDに変更されました。16次車後期
ステンレス車には従来のLCDに加えて、中国語と韓国語専用のLCDも千鳥配置で追加
されました。
運転台は2100形に類似しています。ただし、1800番台は配置が異なります。
ステンレス車の運転台はアルミ車と比べて高くなりましたが、基本的なレイアウトは変更
されていません。
なお、10次車からは運転台に車上情報管理装置(モニタ)が設置されたため、行路表
置き場が600形同様、マスコン左下に変更されました。
なお、2015年後半ごろからは検査入場した際に、運転台にモニタが追加されています。
制御装置
--------------------------------------------------------------------------
アルミ車はシーメンス製のGTO素子またはIGBT素子によるVVVFインバータを採用しま
した。GTO素子のインバータは発車時に独特の音階を奏でることで有名です。前に登場
した2100形もシーメンス製の音階を奏でるインバータを採用していますが、音が異なり
ます。なお、回生失効速度が高いため停車時に逆音階は奏でません。
IGBT素子のインバータは京急で初めて全電気ブレーキ対応とされました。なお、空気
ブレーキの動作タイミングはGTO素子と同じく停止寸前よりも速い速度で動作します。
ステンレス車は東急車輛製の8両編成が三菱製、川崎重工製の4両編成と6両編成が
東洋製のIGBT素子によるVVVFインバータを採用しました。
東洋製の車両は停止寸前まで回生動作しますが、三菱製の車両は回生失効速度が
3〜5km/h程度と高めです。なお、1169編成は三菱製では初めて全電気ブレーキを
採用し、東洋製同様に停止寸前まで回生動作します。
なお、2014年12月より1073編成〜1161編成も順次全電気ブレーキの使用を始めました。
2010年2月5日に、京急では初採用となる東芝IGBTインバータを1405編成に搭載し、
試運転を行いました。なお、この編成以降に出場した編成は今のところ、シーメンスの
まま出場しています。
そして6年がたった2016年3月11日に1401編成が同じく東芝IGBT化され、今後は
本格的に換装が進むものと思われます。なお、新1000形に限らず、従来はVVVFの
換装をする場合は検査と同時に行われていましたが、1401編成についてはVVVFの
単独工事となりました。これにより、シーメンスGTO淘汰は秒読みになったと思われます。
2015年12月に登場した1367編成は新造車では初の東芝製VVVFを採用し、主電動機
にはPMSMを採用しました。
なお、この後に新造された車両はこれらは採用されず、従来通りとされました。
MT比は、1次車〜2次車が8両が4M4T、4両が2M2Tと、新1000形の中では電動車比率が
一番低くなっています。
3次車〜5次車は8両が6M2T、4両が3M1Tと、比率が上がりました。
6次車以降ステンレス車は8両が6M2T、6両が4M2T、4両(1800番台含む)が4Mとなり、
今現在新造車もこの比率です。
この中で特徴的なのはステンレス車の4両編成で全電動車となっています。近年では
再び他社でも全電動車が登場していますが、それらは0.5M車のため、編成全体では
MT比が1:1になるように設計されています。しかし、京急では全ての台車が電動台車と
なっており、純粋な全電動車となっています。なお、全電動車になった理由として、
中間に付随車2両を組み込めば6両にできる構成にしたためです。
次車区分
--------------------------------------------------------------------------
※近年の次車区分がはっきりしないため、当サイト独自区分とします。
1次車(2002年度製※1001編成は2001年度中に落成)
8両編成:1001編成、1009編成、1017編成
4両編成:1401編成、1405編成
1次車は種別、行先表示ともに黒幕で登場しましたが、現在は白幕に交換されています。
なお、1401編成1401号車は試験的にLEDを採用していました。初期は前面部分にも
ローマ字表記がありましたが、後に現在の表示になりました。LED試験終了後は一度、
元の黒幕になった後、現在は他の車両同様、白幕に交換されています。また、同車両は
試験的にシーメンスのIGBT素子によるインバータも搭載していました。現在のシーメンス
のIGBTと比べ低音になっていました。現在は従来のシーメンスのGTOインバータに戻って
います。
1次車は将来の組み換えによる6両編成化を考慮して設計されたため、それに関連して
4両編成はパンタグラフが浦賀寄りが未設置となっています。
扉間の窓は緑色に着色された2枚窓を採用しています。
制御装置はシーメンスのGTO素子によるVVVFインバータが採用されています。
なお、1405編成は2010年2月に東芝IGBTインバータに更新されました。
2次車(2003年度製)
8両編成:1025編成、1033編成
4両編成:1409編成、1413編成
2次車は種別、行先表示ともに登場当時から白幕を採用しています。
2次車からは6両編成化を考慮していません。そのため、パンタグラフの設置箇所等が
変更されています。
2次車からは扉間の窓は黒に着色された1枚窓となり、1次車よりも窓全体の幅が
広がっています。
制御装置はシーメンスのGTO素子によるVVVFインバータを採用しています。
3次車(2004年度製)
8両編成:1041編成、1049編成
4両編成:1417編成、1421編成
3次車は種別、行先表示ともに登場当時から白幕を採用しています。
なお、2009年には全編成がLED化されました。
3次車からは制御装置がシーメンスのIGBT素子によるVVVFインバータに変更されました。
4次車(2005年度製)
8両編成:1057編成
4両編成:1425編成、1429編成、1433編成、1437編成
4次車からは種別はフルカラーLEDに、行先表示は白色LEDに変更されました。また、
運番表示にはオレンジLEDが採用されました。
制御装置はシーメンスのIGBT素子によるVVVFインバータを採用しています。
5次車(2006年度製)
8両編成:1065編成
4両編成:1441編成、1445編成
4次車との変更点はありません。導入時期の違いにより区別されています。
6次車(2006年度製)
8両編成:1073編成
車体材質がステンレス製に変更されました。
扉間の窓は1次車と類似した緑色に着色された2枚窓を採用しています。
制御装置は三菱のIGBT素子によるVVVFインバータを採用しています。
導入当初は客用扉の室内側に黄色いマーキングテープが貼り付けていませんでしたが、
後に、7次車に合わせて貼り付けられました。なお、2012年4月頃からは京急車全ての
車両にマーキングテープが順次貼り付けらていきました。
7次車(2007年度製)
8両編成:1081編成、1089編成
6次車と比べ貫通扉の部分が多少変更されていますが、6次車とほぼ同様です。
制御装置は三菱のIGBT素子によるVVVFインバータを採用しています。
7次車からは導入当初から黄色いマーキングテープが貼り付けられています。
8次車(2008年度製)
8両編成:1097編成、1105編成、1113編成
4両編成:1449編成、1453編成
6、7次車とほぼ同様ですが、優先席付近の床面が青色になり、優先席付近の手すりに
黄色いカバーが取り付けられました。
前述したとおり、8次車からは車側灯が電球式からLED式に変更されました。
8次車からの4両編成は全電動編成となっており、将来中間に付随車2両を追加して6両
編成にできるように設計されています。それに関連してパンタグラフは品川寄りが未設置
となっています。
9次車(2009年度製※1457編成〜1469編成は2008年度中に落成)
4両編成:1457編成、1461編成、1465編成、1469編成、1473編成、1477編成、1481編成、
1485編成
8次車との変更点はありません。
1457編成〜1469編成は平成20年度中に落成しましたが、鉄道事業計画による導入計画
では次年度分になっているので、次年度になるまで営業運転等は行われませんでした。
10次車(2010年度製)
8両編成:1121編成、1129編成、1137編成
4両編成:1489編成
基本的には9次車と同一ですが、京成線乗り入れ対応のために車上情報管理装置を
設置するなどの他、一部が変更されています。
また、新1000形では初めて客用扉上部にLCD式案内表示器が設置されました。
種別LED表示は成田スカイアクセス線を収録し、文字と地の境界が消灯され黒縁という
新表示となっています。
11次車(2011年度製)
8両編成:1145編成
6両編成:1301編成、1307編成、1313編成
新1000形では初めてとなる6両編成が製造されました。内装は10次車同様、客用扉
上部にLCD、運転台には車上情報管理装置が設置されています。システム的には
8次車からの4両編成に中間2両の付随車を入れた仕様になっているものと思われます。
なお、電気連結器は通常運転では使用しないため新造時から既に外されています。
1145編成については、10次車同様にスカイアクセスに乗り入れるための停車駅予報
装置がついています。
1313編成は京急で初めて車内電灯全てにLEDを採用しました。
種別LED表示も10次車同様、黒縁仕様となっています。
12次車(2012年度製)
8両編成:1153編成
6両編成:1319編成、1325編成
11次車との変更点はありません。
13次車(2013年度製)
8両編成:1161編成
6両編成:1331編成、1337編成
12次車との変更点はありません。1337編成の導入を以って新1000形保有数が
300両を超えました。
14次車(2014年度製)
8両編成:1169編成
6両編成:1343編成、1349編成、1355編成
13次車と大きな変更点はありません。
なお、1169編成に関してはステンレス車8両編成としては初めて全電気ブレーキ対応
になりました。
15次車(2015年度製)
6両編成:1361編成、1367編成
4両編成:1801編成、1805編成
1361編成は従来車と大きな変更点はありません。1367編成は京急で初めて主電動機に
PMSM(永久磁石)を採用したほか、新造車では初めて東芝製VVVFを採用しました。
1801編成と1805編成は前面が貫通型に変更され、側面のカラーリングもステンレス車
ながらアルミ車と同じようなデザインになるようにフルラッピングされています。
このように15次車は製造時期により全て仕様が異なり、15次車の線引きが微妙です…。
16次車(2016年度製)
8両編成:1177編成、1185編成
6両編成:1601編成、1607編成
4両編成:1809編成
昨年度1800番台に続き、新たな番台の1600番台を使用した編成が登場しました。
なお、今年度の夏までは1500形が使用していた番台で、半年足らずで1600番台が
再び使用されたことになります。
なお、これまでの6両編成の番台で使用していた1300番台にはまだ空きがあったものの、
残り4編成製造したところで一気に1600番台まで飛んでしまうためなのか、マイナー
チェンジというタイミングで1600番台まで飛びました。
これに合わせて8両編成も1200番台で登場するのではと言われていましたが、こちらは
1000番台から1200番台まで連番で使用できるためか、従来のステンレス車からの
連番で1177編成となりました。そのため、6両編成は1300番台と1600番台で区別して
呼称することができますが、8両編成については番台での区別が一切できません。
6両および8両編成は従来のステンレス車の顔ですが、側面のカラーリングは1800番台と
同じフルラッピング仕様となっています。また、前照灯は京急で新造車では初採用の
LEDが採用されました。なお、一般的な白色LEDとは異なり電球色となっています。
内装も変更されており、客用ドアに化粧板採用、各車両車端部(乗務員室直後を除く)
の片側ずつにボックスシート採用と、若干アルミ車に回帰したほか、LCDは千鳥配置で
2台設置し、左画面では韓国語、中国語の案内が表示されます。また、ボックスシート
にはサービスコンセントが設置されました。
なお、1809編成は従来の1800番台と同じ仕様です。
2016年度の車両は1809編成を除き公式で16次車と発表されているため、
これらは次車区分に間違いは絶対にありません。
運用
--------------------------------------------------------------------------
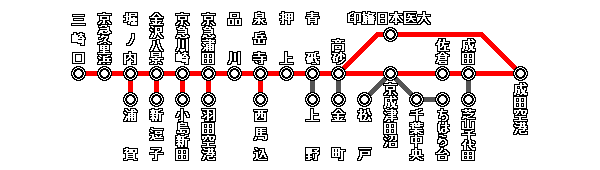
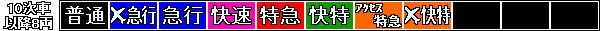
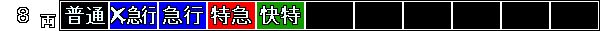
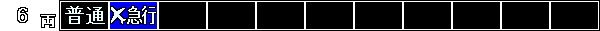
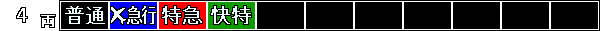
×=エアポート
※アクセス特急および佐倉運用を除き、アルミ車とステンレス車の運用の区別は
ありません。
ただし、4+4の運用はアルミ+アルミ、ステンレス+ステンレス、1800+1800で合わせ
られることが殆どです。また、1、2次車が集中的に充当される運用も存在するようです。
新1000形は京急全線で使用されるほか、都営浅草線・京成線・北総線・成田スカイ
アクセス線に直通しています。種別は、普通・×急行・急行・快速・特急・快特・
アクセス特急・×快特で使用されています。詳細は下記の通り。
8両編成は主に都営浅草線・京成線・北総線直通の普通・×急行・急行・特急・快特に
使用されています。大師線を除き京急全線で見ることができます。
10次車からの8両編成については、成田スカイアクセス線にも直通しているため、
上記種別に加え、アクセス特急・×快特にも使用されてるほか、京成本線系統の運用
にも就いているため、快速でも使用されています。営業運転としては佐倉までですが、
回送で宗吾参道へも入線しています。また、成田空港からも回送で宗吾参道へ
入線する運用もあります。
なお、1177編成以降は何か問題があるのか、京急線内のみの運転となっており、
泉岳寺にすら乗り入れていないため、朝晩の品川発着の優等と横浜方面エア急のみの
運転と、今のところは完全に2000形と同じ立ち位置となっています。
6両編成は主に京急線内の普通・×急行に使用されています。
大師線と久里浜線京急久里浜〜三崎口を除く全線で見られます。
4両編成は主に京急線内の普通車や快特・特急の増結に使用されています。また、2本
以上繋げて快特・×急行・特急・普通にも使用されています。本線(品川〜泉岳寺
を除く)・逗子線・空港線・大師線で見ることができます。
1800番台の車両は先頭車同士幌で繋げられるため、都営線方面にも乗り入れ
可能となっていますが、現状ではそもそも幌を装着しておらず、8両編成が不足しない
限りは直通列車に充当されることはありません。なお、今までに車両不足で8両固定に
なったことはなく、出場時と、登場して少ししてから試験的に直通運転に充当されたこと、
試乗会として運転されたこと、初日号とその数日間運転されただけです。
なお、1800番台は登場からしばらくは4両単独で運転されることはほぼなく、8両編成に
増結され特急か快特、相方と組んでエア急のみの運転となっており、エア急の入出庫
関係の普通車以外では普通車に充当されない異質の運行となっていました。
以前は4+4で×快特にも使用されていましたが、2012年1月に8両固定に車両変更され、
消滅しました。ただし、ダイヤ乱れではその後も就くことがありました。
なお、夏季節電ダイヤ中は一部の×急行に4両単独で充当されていました。
1500形・2000形・600形・2100形・新1000形と連結することができます。なお、6両編成は
電気連結器を装備していないため、通常運転では連結することはできません。
LED化
--------------------------------------------------------------------------
2009年(平成21年)12月よりLED化工事が行われました。LED化の対象となったのは
3次車のみです。
なお、LED化単独工事で行っているため、工事期間は5〜7日程度で完了しています。
2014年12月19日頃より、1次車・2次車の前面運番、種別、行先表示器が順次LED化
されました。
従来の新1000形タイプではなく、600形と同じタイプを採用している模様ですが、600形
よりもシャッタースピードに弱く、実際のところ不明です。
LED日本語・英字交互表示化
--------------------------------------------------------------------------
2010年3月より、LED編成の日本語・英字交互表示化が開始されました。現在は
全編成交互表示化はすべて完了しています。
なお、回送など営業車以外も交互表示します。
その他
--------------------------------------------------------------------------
シーメンス製のインバータを搭載した車両は雨の日はかなり空転します。
シーメンス製のインバータを搭載した車両は低速域から中速域にかけての低音がかなり
うるさいです。IGBTもIGBTとは思えないほど変調してうるさいです。
新1000形の正式名称は1000形ですが、旧1000形が残っている中製造されたので通称と
して新1000形となっています。通称は新1000形の他にN1000形という場合もあります。
また、ステンレス車は銀千や(N1000形に対して)S1000、単純に銀やステンレスという
場合もあります。
厳密に言うと新1000形となるのはデハ1000形のみで、旧1000形に存在していない
サハ1000形は新ではありません。ですが、こんな細かい区別は誰もしません。
ステンレス車の4両編成は晴れの日でも減速力が若干、不安定です。
風圧に耐えられないのか時々、助手席側のワイパーが外側にはみ出ていることが
あります。
2012年6月、1325編成にステンレス車では初となるラッピング電車が運転開始しました。
ノルエコラッピング電車です。
2014年5月より、1057編成が黄色一色(客用扉はグレー)の塗装になり、
KEIKYU YELLOW HAPPY TRAINとして運行開始しました。
新1000形の特別塗装は今回が初となります。
|


![]()
![]()